 私は高校時代、バレーボールをしていました。ケガをして、病院に行くたびに関わってくれる看護師さんにとても助けられた経験があります。その時に見た看護師さんの優しい姿に憧れて看護師を目指すようになりました。記憶にはなかったのですが、看護学生の時、10歳の頃に将来の夢をとして描いた「20歳の私」という絵を見る機会があり、それが看護師だったことに驚き、潜在的に看護師を目指していたことがわかり感動しました。しかし、現実はそう甘くはありません。新人の頃、覚えなくてはならないことも多く、やるべき仕事をこなすのに精一杯で、患者さんに余裕をもって接することができず、葛藤の毎日でした。患者さんやご家族の意見や指摘に対して病棟スタッフみんなで一生懸命考えて改善しているつもりでしたが、意見や意向が分かり合えず、自信につながらない日々を送っていました。しかし、最初から正解を先輩たちに求めるのではなく、まず自分で考えることを習慣化し、自分の意見を先輩たちに伝えた上で、他にどのような考え方があるのか、意見交換をするようにこころがけました。患者さんを看て、自分でアセスメントをする習慣を身に付けることで、自分は看護師であると自覚するとともに、成長につながったと考えます。
私は高校時代、バレーボールをしていました。ケガをして、病院に行くたびに関わってくれる看護師さんにとても助けられた経験があります。その時に見た看護師さんの優しい姿に憧れて看護師を目指すようになりました。記憶にはなかったのですが、看護学生の時、10歳の頃に将来の夢をとして描いた「20歳の私」という絵を見る機会があり、それが看護師だったことに驚き、潜在的に看護師を目指していたことがわかり感動しました。しかし、現実はそう甘くはありません。新人の頃、覚えなくてはならないことも多く、やるべき仕事をこなすのに精一杯で、患者さんに余裕をもって接することができず、葛藤の毎日でした。患者さんやご家族の意見や指摘に対して病棟スタッフみんなで一生懸命考えて改善しているつもりでしたが、意見や意向が分かり合えず、自信につながらない日々を送っていました。しかし、最初から正解を先輩たちに求めるのではなく、まず自分で考えることを習慣化し、自分の意見を先輩たちに伝えた上で、他にどのような考え方があるのか、意見交換をするようにこころがけました。患者さんを看て、自分でアセスメントをする習慣を身に付けることで、自分は看護師であると自覚するとともに、成長につながったと考えます。
入院生活の中でもできるだけ、自分らしい生活してもらえるように創意工夫をしていきたい
私は、常に患者さんの生活を大事に思い看護をしています。入院生活は普段の生活と比べると違和感があるでしょう。具体的には、できるだけ家で生活していた時と近いリズムで生活してもらいたいと思っています。そこで、家で何をしていたのかを何気なく聞くようにしています。1日の過ごし方や好きなことを、入院生活の中でも、自分らしい生活に近づけるようにと考えています。例えば、畑仕事をしている人、庭で草取りをしている人には、その時間にリハビリをしてもらったり、動く時間を作ります。運動ができない人であっても、座る時間を作り、塗り絵など何か作業をしてもらうようにしています。そして、夜はしっかり睡眠をとってもらい、生活リズムを整えるようにしました。高齢の患者さんも多く、認知症やせん妄を発症することもあるため、生活リズムを整えることは、それらの予防にもなると思い、大切に考えています。最近は、退院支援の勉強に力を入れています。入院生活だけでなく、退院してからもその人らしさを大切にして生活ができるようにするためにどうすればよいかという視点を意識するようになりました。特に、コロナ禍で、家族との面会もままならない状態で、患者・家族がどうしたいのかということについて、お互いの橋渡し役として適切な提案ができるようになりたいと思っています。
これまで先輩たちにして頂いたことと同じように後輩たちに接し、一緒に成長していきたい
看護師になって5年目を迎えましたが、まだ今後どのようなことにチャレンジをしていこうか決めることが出来ていません。今後どのような看護師になっていくのかを考えながら、基本的なことも含めてまだ足りていない知識や技術の習得をする段階にいると思っています。ただ、そうは言っても、後輩たちから見ると5年目の先輩ということになります。自分がこれまで先輩たちにして頂いたことと同じように後輩たちに接していきたいと思っています。後輩たちには、同期の人だけでなく、先輩達に対して積極的にコミュニケーションするようにアドバイスしたいとともに、その点をフォローしていきたいです。先輩に確認・相談することは自分の判断が正しいかどうかを学ぶことができます。また、自分の判断が正しくても、異なる考えや捉え方を知る機会になり、その時の学びはとても大きいと感じています。先輩と言っても看護師だけではなく、リハビリや薬剤師など多職種の先輩たちとも積極的コミュニケーションをしてもらいたいと思います。そして、私自身後輩とのコミュニケーションや指導を苦手としています。この苦手を克服して、後輩たちとともに、私も成長していきたいと思います。

 私が看護師になろうと思ったきっかけは、小学生の頃、兄が入院した際の両親の姿でした。患者家族の大変さを間近で見ていた私は、患者はもとより家族に対してもケアができる看護師になりたいと思うようになりました。高校進学と同時に看護を学ぶことになりました。患者さんとたくさん話して、役に立ちたいと思い描いていましたが、新人看護師の頃は覚えなければならない業務をこなすのに精一杯で、しっかりと患者さんの話を聴きたいと思っていても、なかなかその状態に至らず、未熟さにジレンマを感じていました。その後、外科から救命救急に異動しても、「まだまだだなあ」を感じながら働いていました。しかし、看護師の仕事を辞めたいと思ったことはなく、患者さんの笑顔や「ありがとう」という言葉、先輩や同期の仲間たちに支えられ、やりがいを少しずつでも感じながら仕事に取り組んでいました。患者さんとしっかりとコミュニケーションを取り、家族を支える先輩を見て、勇気づけられてきました。育休期を終え、呼吸器内科で看護をしていますが、患者さんと以前よりはしっかり話せるようになり、看護の喜びを一層感じるようになりました。
私が看護師になろうと思ったきっかけは、小学生の頃、兄が入院した際の両親の姿でした。患者家族の大変さを間近で見ていた私は、患者はもとより家族に対してもケアができる看護師になりたいと思うようになりました。高校進学と同時に看護を学ぶことになりました。患者さんとたくさん話して、役に立ちたいと思い描いていましたが、新人看護師の頃は覚えなければならない業務をこなすのに精一杯で、しっかりと患者さんの話を聴きたいと思っていても、なかなかその状態に至らず、未熟さにジレンマを感じていました。その後、外科から救命救急に異動しても、「まだまだだなあ」を感じながら働いていました。しかし、看護師の仕事を辞めたいと思ったことはなく、患者さんの笑顔や「ありがとう」という言葉、先輩や同期の仲間たちに支えられ、やりがいを少しずつでも感じながら仕事に取り組んでいました。患者さんとしっかりとコミュニケーションを取り、家族を支える先輩を見て、勇気づけられてきました。育休期を終え、呼吸器内科で看護をしていますが、患者さんと以前よりはしっかり話せるようになり、看護の喜びを一層感じるようになりました。 私が看護師になろうと思ったのは、看護師になりたかった母親の勧めがきっかけです。祖母が亡くなった時に、看護師になろうと決心しました。看護師として働き出した頃は、私のおっちょこちょいなところが顔を出し、ミスが多く、上司や先輩によく叱られていました。やはり、仕事に慣れていない、覚えることが多い、どうしても時間が掛かり忙しくなるので、振り返る時間も取れない状態でしんどい毎日でした。しかし、徐々に仕事も覚え、慣れてくるとミスを防ぐことができるようになり、入職した頃のことが嘘のようでした。振り返ると、叱られていたのではなく、しっかりと指導してもらっていたと思います。そして、3年目になるとリーダーとして仕事を任されるようになりました。自分の仕事だけでなく、周りの仕事にも目を配ることが必要になりました。そのことで、狭い視野で仕事していた自分が、広い視野で仕事を捉えることができるようになり、看護をする楽しみが増えました。後輩が入ることで、これまで以上に勉強することも楽しくなり、自分がやらねばという意識だけでなく、しっかりとやってもらえるようにすることも大事だと気づき、後輩たちのおかげで自分の成長があると実感しています。
私が看護師になろうと思ったのは、看護師になりたかった母親の勧めがきっかけです。祖母が亡くなった時に、看護師になろうと決心しました。看護師として働き出した頃は、私のおっちょこちょいなところが顔を出し、ミスが多く、上司や先輩によく叱られていました。やはり、仕事に慣れていない、覚えることが多い、どうしても時間が掛かり忙しくなるので、振り返る時間も取れない状態でしんどい毎日でした。しかし、徐々に仕事も覚え、慣れてくるとミスを防ぐことができるようになり、入職した頃のことが嘘のようでした。振り返ると、叱られていたのではなく、しっかりと指導してもらっていたと思います。そして、3年目になるとリーダーとして仕事を任されるようになりました。自分の仕事だけでなく、周りの仕事にも目を配ることが必要になりました。そのことで、狭い視野で仕事していた自分が、広い視野で仕事を捉えることができるようになり、看護をする楽しみが増えました。後輩が入ることで、これまで以上に勉強することも楽しくなり、自分がやらねばという意識だけでなく、しっかりとやってもらえるようにすることも大事だと気づき、後輩たちのおかげで自分の成長があると実感しています。 副看護師長 長谷川瑠璃
副看護師長 長谷川瑠璃 看護師長 本夛やよい
看護師長 本夛やよい 小学生の頃からドラマを観て看護師に憧れていました。家族や親戚にも医療職をしている者はいませんが、祖母と一緒に暮らしていたので、その話をしたら応援してくれました。実は、祖母は看護師になりたかったらしく、自分がなれなかったので応援してくれました。そして、看護学校に進学して、看護師になりました。実際に看護師になってみると、憧れていたイメージとはかけ離れたものでした。先輩たちの指導を厳しく思うことや、患者さんの希望に沿えないこともたくさんありました。例えば、自分がはっきりと理解していない状態で検査や処置を観察していると、「分からない状態でやろうとしたのですか、責任は持てますか」と叱責を受けました。こういった指導は新人の時は厳しく感じるので、看護師をやっていけるのだろうかと思っていました。些細なことで落ち込んだり高揚したりの繰り返しで、もう少し頑張ろうと思い続けていました。振り返ると指導が厳しいのではなく当然のことを教えられただけで、自分が甘かったのだと思います。それでも、徐々に患者さんとコミュニケーションが取れるようになり嬉しい瞬間も増えてきました。
小学生の頃からドラマを観て看護師に憧れていました。家族や親戚にも医療職をしている者はいませんが、祖母と一緒に暮らしていたので、その話をしたら応援してくれました。実は、祖母は看護師になりたかったらしく、自分がなれなかったので応援してくれました。そして、看護学校に進学して、看護師になりました。実際に看護師になってみると、憧れていたイメージとはかけ離れたものでした。先輩たちの指導を厳しく思うことや、患者さんの希望に沿えないこともたくさんありました。例えば、自分がはっきりと理解していない状態で検査や処置を観察していると、「分からない状態でやろうとしたのですか、責任は持てますか」と叱責を受けました。こういった指導は新人の時は厳しく感じるので、看護師をやっていけるのだろうかと思っていました。些細なことで落ち込んだり高揚したりの繰り返しで、もう少し頑張ろうと思い続けていました。振り返ると指導が厳しいのではなく当然のことを教えられただけで、自分が甘かったのだと思います。それでも、徐々に患者さんとコミュニケーションが取れるようになり嬉しい瞬間も増えてきました。 副看護師長 鈴木美香
副看護師長 鈴木美香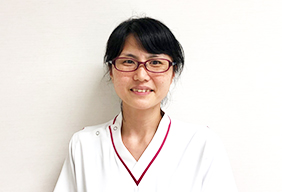 中学生の頃、親元を離れて長い間一人で入院した時にある看護師が親代わりに支えてくれました。その看護師から「あなたは看護師に向いているかもね」という一言を真に受け、また、その方に憧れて看護師になろうと思いました。実際に看護師なり、新人の頃は何が正しいのか、間違っているのかさえわからない、報告することもままならない状態でした。頑張っているのに何度も注意されショックを受けていました。夜勤をするようになり、ゆっくりとカルテを見たり、色々な患者さんを看たり、先輩看護師が報告しているのを見て、徐々に異常が何かがわかってきました。看護に楽しみを感じるようになったのは3年目のリーダーになってからです。リーダーになってから周りが見えるようになり、例えば、医師の考えがわかるようになると何でこの薬なのかなとか、何故この指示なのかなとカルテを見て考えるようになりました。新人の最初の3ヶ月は暗中模索でしたが、3年目には看護の楽しみがどんどん増えて来ました。今、新人に対してはわからないことが前提で話をし、反応を見て、わかってない部分を掘り下げるようにしています。
中学生の頃、親元を離れて長い間一人で入院した時にある看護師が親代わりに支えてくれました。その看護師から「あなたは看護師に向いているかもね」という一言を真に受け、また、その方に憧れて看護師になろうと思いました。実際に看護師なり、新人の頃は何が正しいのか、間違っているのかさえわからない、報告することもままならない状態でした。頑張っているのに何度も注意されショックを受けていました。夜勤をするようになり、ゆっくりとカルテを見たり、色々な患者さんを看たり、先輩看護師が報告しているのを見て、徐々に異常が何かがわかってきました。看護に楽しみを感じるようになったのは3年目のリーダーになってからです。リーダーになってから周りが見えるようになり、例えば、医師の考えがわかるようになると何でこの薬なのかなとか、何故この指示なのかなとカルテを見て考えるようになりました。新人の最初の3ヶ月は暗中模索でしたが、3年目には看護の楽しみがどんどん増えて来ました。今、新人に対してはわからないことが前提で話をし、反応を見て、わかってない部分を掘り下げるようにしています。